電子帳簿保存法、対応できていますか?中小企業が抱えがちな課題と解決策
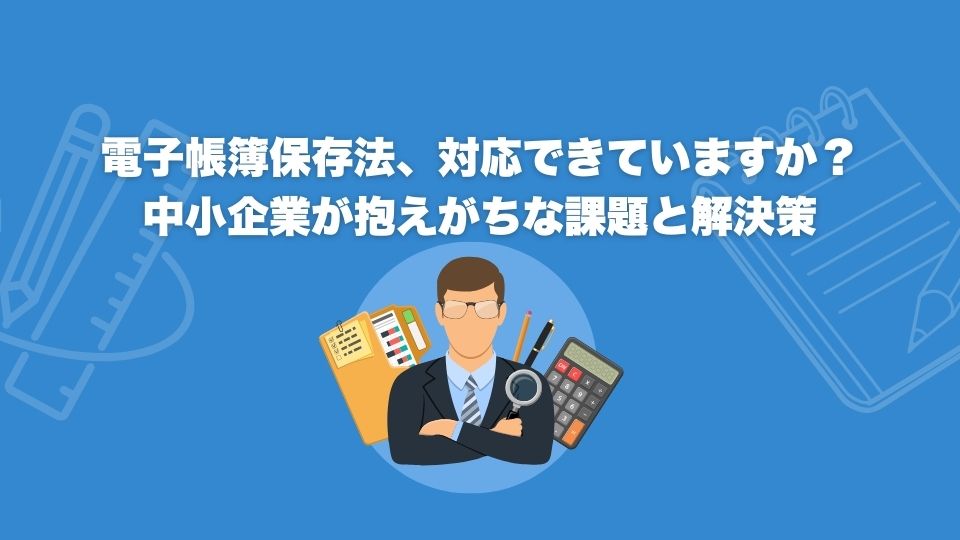
Contents
1.電子帳簿保存法、何が問題?なぜ今注目されているのか
「電子帳簿保存法、対応しないといけないのはわかってるけど、うちはまだ何も手を付けていない…」
そんな声が、今、中小企業の経営者から多く聞かれるようになっています。
実はこの電子帳簿保存法(電帳法)、単なる「書類の保存ルール変更」ではありません。対応しないことが“リスク”に直結する法律なのです。
🔍 なぜ今、注目されているのか?
もともと1998年に施行されたこの法律は、紙で保存していた帳簿や書類を、電子データで保存できるようにすることを目的としたものでした。
しかし近年、インボイス制度の開始・テレワークの普及・電子取引の増加などを受けて、電帳法の内容も大きく見直され、**2024年1月から原則「電子取引は電子保存が義務」**となりました。
つまり、
📧 PDFの請求書や見積書をメールで受け取って保存している場合でも、
✅ 紙に印刷して保存するだけでは違反になる可能性があるということです。
⚠️ 対応しないとどうなる?
「税務署からの指摘」や「青色申告の承認取り消し」など、罰則的なリスクがあるだけでなく、調査時に正しい帳簿保存がされていなければ、必要以上の税金を支払う結果になることもあります。
加えて、社内での対応が遅れることで、
- 書類の探しづらさ
- 保存ミスによるデータ欠損
- 担当者による対応のバラつき
など、日々の経理業務自体が非効率になってしまうという問題も発生します。
✅ でも、正しく対応するのは意外と難しい
「じゃあ、すぐ電子保存に切り替えよう!」と思っても、現実には簡単ではありません。
- どの帳票が対象なのか?
- どんな保存要件を満たさないといけないのか?
- どんなシステムを使えばいいのか?
これらをすべて把握して対応するには、法令知識と実務の両方が必要になります。
だからこそ今、「経理代行」や「クラウド会計の導入サポート」を活用して、専門家に任せる企業が増えているのです。
2. 電子帳簿保存法の基本と、2024年以降のポイント
電子帳簿保存法(通称:電帳法)は、「電子で受け取ったデータは電子のまま保存しなさい」というルールが明文化された法律です。
2024年1月からは「電子取引データの電子保存が義務化」され、これまで“紙に印刷して保存しておけばOK”だった方法が通用しなくなっています。
対応していない中小企業にとっては、知らず知らずのうちに違法状態になっている可能性もあるのです。
🔍 電帳法が対象とする3つの保存区分
電子帳簿保存法では、保存する対象が大きく3つに分かれています。
| 区分 | 内容 | 義務化状況 |
| ① 電子帳簿等保存 | 仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿を電子データで保存 | 任意(紙でも可) |
| ② スキャナ保存 | 紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして電子保存 | 任意(要要件) |
| ③ 電子取引データ保存 | メール・Webで受け取るPDF請求書、EDI、ネットバンキングの明細など | 原則義務(2024年1月〜) |
🧾 一番の注意点は「③ 電子取引データ保存」
ここで注意したいのは、電子で受け取った取引データの保存方法です。
例えばこんなものが対象になります:
- メール添付で受け取った請求書(PDF)
- クラウドサービス上で発行・保存される見積書・注文書
- オンラインバンキングの取引履歴
- 電子請求書発行サービス(例:マネーフォワード、freeeなど)の出力データ
これらを、印刷して紙で保存しておくだけでは“違反”扱いになります。
✅ 電子保存に求められる「保存要件」とは?
ただ保存するだけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
| ① 真実性の確保 | タイムスタンプ付与、履歴管理、改ざん防止機能など |
| ② 可視性の確保 | パソコン等で画面表示が可能なこと |
| ③ 検索機能の確保 | 日付・金額・取引先で検索できるようにすること(一定条件下で緩和あり) |
これらをすべて満たさないと、電子保存していても「法令違反」となってしまうのです。
つまり、適切な仕組みを作らないと“保存したつもり”が通用しないというわけです。
🧩 何が問題なのか?どこが難しいのか?
- 「対象書類がわからない」
→ どの書類が電子保存義務の対象なのか、判断できていない企業が多数。 - 「要件が複雑すぎて、自社対応が無理」
→ 検索機能やタイムスタンプなどの技術的な対応が難しい。 - 「今の経理フローと噛み合わない」
→ 紙中心の業務フローを変更せずに対応しようとすると、かえって混乱。
💡 だから必要なのは、「仕組みと専門知識の両方」
電帳法に対応するには、単にクラウド会計ソフトを導入するだけでは不十分です。
どの帳票に、どの保存方法が必要なのか?
どのツールを使えば、要件を満たせるのか?
今の業務フローをどう見直せば、スムーズに運用できるのか?
こうした法務・IT・実務すべてにまたがる知識が求められるため、外部の専門家と連携した対応がいま注目されています。
3. 中小企業が抱える3つの悩みと落とし穴
電子帳簿保存法への対応が義務化されたとはいえ、現実的に「何から手をつければいいのか分からない」という中小企業が非常に多いのが実情です。
ここでは、実際に多くの中小企業が抱えている**“よくある3つの悩み”と、そこに潜む落とし穴**を紹介します。
「うちもこの状態かも…」と思い当たる方は、早めの対策が必要です。
❶ システム選定ができない
🔎 ありがちな悩み:
「電子保存って言うけど、何をどう保存すればOKなのかが分からない」
「クラウド会計とかあるけど、うちに合ってるのはどれ?」
システム導入は簡単そうに見えて、実は選び方ひとつで対応可否や作業効率に大きく差が出ます。
💥 よくある落とし穴:
- 安価なツールを入れたが、保存要件を満たしていなかった
- 会計ソフトと連携できず、手入力が発生して結局アナログ作業に逆戻り
- 複数ツールを入れてしまい、情報がバラバラに管理されてしまう
❷ 社内の業務フローがアナログのまま
🔎 ありがちな悩み:
「うちの取引先はFAXが多くて…」「社内で紙文化が根強く残ってる」
「経理担当がエクセルでがんばってるから、変えるのも不安」
このように、そもそも紙を前提とした業務フローが出来上がってしまっている企業では、電子保存に移行するのが大きな壁となります。
💥 よくある落とし穴:
- 紙と電子が混在し、どれをどう保存するか社員が混乱
- 結局「印刷してファイリング」で対応してしまい、法令違反に
- 担当者頼みになり、属人化してしまう
❸ 実務に落とし込めず、結果的に“放置”
🔎 ありがちな悩み:
「情報は色々集めたけど、結局忙しくて対応が後回しに…」
「何が正解か分からないまま、“とりあえず今まで通り”で動いている」
実務に落とし込むためには、システム・社内体制・人材教育の3つがそろって初めて機能します。
ひとつでも欠けると、現場では動かず、結局“放置”状態に。
💥 よくある落とし穴:
- 気づけば義務化から1年以上が経過、対応していないこと自体を忘れていた
- 税務調査で突然の指摘 → 是正対応に多額のコストと時間
- 「対応できている」と思っていたが、実は保存要件を満たしていなかった
📌 小さなズレが、後々“大きなミス”に
電子帳簿保存法は、一見すると小難しいルールに見えますが、実はひとつの対応ミスで大きなリスクが発生する法律です。
中途半端な理解で導入を進めたり、未対応のまま業務を続けてしまうと、のちのち「時間・コスト・信頼」の3つを大きく失うことにもなりかねません。
4. 経理代行×クラウド会計導入が選ばれている理由
電子帳簿保存法の対応を進める上で、
「システムも必要、運用の見直しも必要、さらに業務の実行も…」
――これをすべて社内だけで担うのは、現実的に非常にハードルが高いのが実情です。
そこで今、中小企業の“実務負担と法対応”の両方を解決する手段として注目されているのが、
「経理代行」と「クラウド会計導入支援」の組み合わせです。
✅ ① 保存要件に沿った仕組みづくりをプロが設計してくれる
電子帳簿保存法は、単に「データを保存する」だけでは不十分。
「改ざん防止」「検索機能」「可視性」など、複数の保存要件を満たす必要があります。
経理代行会社は、
- どの書類が電子保存の対象か?
- どのツールを使えば保存要件を満たせるか?
- どんな業務フローに変更すべきか?
といった点を、税務・会計・ITの専門知識に基づいてアドバイス・設計してくれるため、
「制度を守るための仕組みづくり」から安心して任せることができます。
✅ ② 業務の「実行」まで代行してくれるから、ラクに続けられる
経理代行の最大の強みは、仕組みを作るだけでなく、実際の経理業務もまるっと任せられる点です。
例えばこんな業務を代行可能です:
- 請求書や領収書の電子保存・分類
- クラウド会計ソフトへのデータ入力・確認
- 月次レポートの作成や帳簿管理
- 仕訳・振込・支払管理などの定型業務
つまり、「ルールどおりに処理しなきゃ」と毎月悩む必要がなくなるわけです。
その分、経営者は本来注力すべき経営判断や売上活動に集中できます。
✅ ③ クラウド会計との連携で、業務もスピードも劇的に改善
クラウド会計ソフト(例:freee、マネーフォワードなど)と連携することで、
経理代行とリアルタイムで情報共有でき、
- 取引データの自動取り込み
- 領収書の自動仕訳
- スマホやPCからいつでも帳簿確認
など、スピーディーで透明性の高い経理体制が実現します。
もちろん、これらのツール導入・初期設定も代行会社が対応してくれるため、
「導入したけど使いこなせなかった」という心配もありません。
💬 実際に導入した企業の声
「法改正が多すぎて追いつけなかったけど、経理代行に相談したらすべて対応してもらえて本当に助かっています。毎月の経理の不安がなくなりました。」
— 製造業・経営者(従業員20名)
「クラウド会計と連携したことで、紙のやりとりが激減。請求書の電子保存も完全にお任せで、気がついたら税務対応までスムーズになっていました。」
— 建設業・経理担当者
🔍 「やることが多すぎる」なら、外注は“守りの経営判断”
電子帳簿保存法は、やらなければならない。
でも、社内だけで何とかしようとして、結局中途半端に終わってしまう…
――そんな状態を避けるためにも、信頼できる外部パートナーに任せることは、経営の“守り”として非常に有効な判断です。
5. まとめ
電子帳簿保存法はすでに義務化されており、対応しなければ税務リスクや業務効率の低下につながる可能性があります。
とはいえ、
- どこから手を付ければいいのか分からない
- ツール選定や設定が難しい
- 現場に負担をかけたくない
という中小企業が多いのも現実です。
そんなときこそ、経理代行とクラウド会計の導入支援を活用するという選択肢があります。
仕組みづくりから運用、日々の経理業務まで、プロがまるごとサポートします。
📩 「うちもそろそろ対応しないと…」と思ったら、お気軽にご相談ください!
無料相談・診断を受付中です。御社に合った対応方法をご提案いたします。
