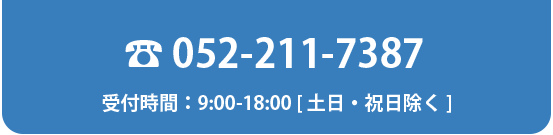ルールとマニュアルの整備
なぜルールとマニュアルが必要なのか?
会社が成長するにつれて、経理業務は複雑になります。その際、明文化されたルールやマニュアルがなければ、業務が属人化し、ミスやトラブルが発生しやすくなります。
逆に、しっかりと業務ルールが整備されていれば、誰が担当しても一定の品質が保たれ、業務の引き継ぎや外注もしやすくなります。
社内ルールの明文化(例:経費精算のルール)
以下のような項目について、ルールを文書にしておくとよいでしょう。
経費精算ルールの例:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 月末締め・翌月5日までに提出 |
| 必要書類 | 原則として領収書を添付(レシート不可の場合は理由を記載) |
| 支払方法 | 原則として会社指定カード使用、やむを得ない場合は立替可 |
| 対象経費 | 交通費・交際費・通信費など(明確に定義) |
そのほか、請求書の発行ルールや印刷・押印の運用方法なども決めておくと混乱が防げます。
業務マニュアルの作り方とテンプレート例
マニュアルを作成する際のポイントは、「誰が読んでも迷わず作業できる」ようにすることです。
マニュアル構成の基本:
目的と概要
この業務は何のために行うのか
担当者
誰がいつやるのか(代行者がいる場合はその名前も)
手順
具体的な作業手順(スクリーンショット付きが望ましい)
チェック項目
ダブルチェックのポイントや、よくあるミス
【業務名】 取引先への振込処理
【目的】 支払期日に遅れず正確に振込を行う
【実施タイミング】 毎月10日・25日(定期支払日)
【手順】
1. 会計ソフトで未払一覧を確認
2. インターネットバンキングで振込予約
3. 上長に内容を確認してもらう
4. 実行後、振込控えをPDFで保存
【確認ポイント】 金額・振込先の入力ミスがないか
誰が、いつ、何をするかの役割分担
ルールやマニュアルを定めたら、それを「誰が実施するか」まで落とし込む必要があります。
経理業務の役割分担例:
| 業務 | 担当者 | 補足 |
|---|---|---|
| 領収書の回収 | 全社員(提出者) | 月末提出を義務化 |
| 経費精算チェック | 経理担当者 | 不備があれば差戻し |
| 会計入力 | 経理または外注先 | 会計ソフトに記録 |
| 月次確認 | 代表 or 管理職 | 試算表チェック |
これらの整備を通じて、経理の業務設計が「属人的な作業」から「再現可能な仕組み」に変わります。結果として、ミスの削減、業務の効率化、トラブルの防止につながるのです。
税理士・外部パートナーとの連携
どこまで自社でやるか、どこから外注するか
会社設立直後は、リソースが限られているため、経理業務の一部または全部を外部に依頼するのが一般的です。以下のように、業務の内容に応じて「内製」「外注」を使い分けることが重要です。
自社でやるべき業務(内製化が向いている):
- 領収書・請求書の収集
- 銀行口座やクレカの明細チェック
- 経費精算の初期確認
外部委託が有効な業務:
- 会計ソフトへの仕訳入力(記帳代行)
- 月次・年次決算の作成
- 税務申告(法人税・消費税)
- 給与計算・年末調整
ポイントは「仕訳までは自社、それ以降は税理士」という分担がコストと効率のバランスが良いとされています。
税理士の選び方と契約ポイント
税理士と契約する際は、以下の点をチェックしましょう。
選ぶ際のチェックリスト:
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| 業種に理解があるか | 自社のビジネスモデルに精通しているか |
| クラウド会計に対応しているか | freeeやマネーフォワードに慣れているか |
| 料金体系が明確か | 月額報酬・決算料などが明確かつ妥当か |
| コミュニケーション方法 | チャットやZoomなど、相談のしやすさ |
| 相性が良いか | 初回面談でフィーリングを確認することも重要 |
契約時のポイント:
- 契約内容を書面化(業務範囲、料金、納期など)
- 決算報酬がいくらか、追加料金が発生する条件も確認
- 途中で変更可能かどうか(契約期間、解約条件)
コミュニケーションの取り方と注意点
税理士との良好な関係を築くためには、継続的でスムーズな情報共有が欠かせません。
情報共有のコツ:
- 月に1回、会計データを共有するルーチンを作る
- 疑問点は早めに相談し、解決する
- 資料提出の期限を守る(例:領収書は翌月5日までに提出)
よくあるトラブルと対処法:
- 資料の遅れ:チェックリストを用意し、漏れを防ぐ
- 認識の違い:やり取りはメールやチャットで記録を残す
- 報酬トラブル:契約書で範囲と費用を明確にしておく
適切なパートナーと連携することで、経理の「わからない」「できない」部分を補い、経営に集中できる環境が整います。
新規設立した会社において、経理業務は後回しにされがちですが、早い段階で業務設計を整えることは、経営の安定と成長に直結する重要なステップです。
今回ご紹介したように、経理業務には明確な流れがあり、何を管理するのか(業務の全体像)
どのツールを使うのか(会計ソフト・補助ツール)、どういう手順で進めるのか(業務フロー)、どのように人が関わるのか(ルールとマニュアル)、誰と連携するのか(税理士・外部パートナー)という5つの視点を押さえておくことで、経理の「仕組み化」が実現できます。
特に経理業務は、正確性と継続性が命です。設立初期の段階から仕組みを整えておけば、日々の業務がスムーズになるだけでなく、融資や資金調達、将来的な成長時にも強い体制を築くことができます。
最初は完璧を目指す必要はありません。小さく始めて、少しずつ改善していく。それが、経理業務の設計において最も現実的で効果的なアプローチです。